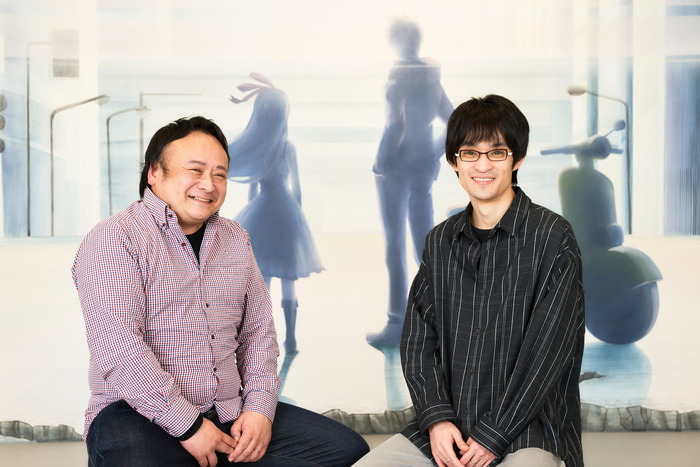■苦労といえば「本読み中のケンカ」?
――(笑)。とはいえ、先日のゲームスタッフサイドの座談会では下田さんから「この人たちと一緒に仕事ができて本当によかった」というお言葉もありました。いきなり壁に直面したアニメ制作をどんなふうに乗り越えていったのでしょうか?
宮
乗り越えるというか、少しずつピースを組んでいくしかなかったです。
そんななかで、キャラクターの描き方が見えてきました。現実に生きている僕らは、未来の出来事が想像できないですよね。推測はついたとしてもそのとおりになる保証もありません。
だけど、それこそが生きているということだと思うんです。『消滅都市』のキャラクターも予定調和で動いていたら面白くない。
未来がわからないなかで生きている姿こそが、生々しくて観る人に没入感を与えると思うんです。
――そういう要素をキャラクターに持たせていったと。
宮
キャラクターを立体的に構築していく作業ですね。
ユキもタクヤも、現実的な人格を持った人物として描いています。現実の僕らって、常に本音を言っているわけではなく、嘘を含みながら真実を伝えることもあるはずです。
怒っているとき怒っている顔をするとは限らないし、悲しいときだって悲しい素振りを見せないときもある。本当は今言いたいだろうけど、我慢する。それが人間というものだと思うし、ユキとタクヤもそうであるだろうと。
なので、生きて死ぬことが課せられている生(なま)の存在として描いています。

――世界観と同じく、キャラクターもリアルですね。
宮
下田さんがつくられた世界観やキャラクターも、シビアで現実に則した僕らの地平の先にあるものです。なのでキャラクターに嘘があると、何やっても心躍らないしハラハラしない。
なのでまずは、「タクヤってこういうときこういう反応するんだ」「ユキはどうなるんだろう?」という各々の生の体験をイメージしていく作業が必要になりました。
――予定調和のないキャラクターを描くとなると、シナリオの打ち合わせも大変だったでしょうか。
宮
ええ、流れもなかなか繋がらなかったし、要素が多過ぎて雑然としてしまう懸念もありました。
でも、やっぱり僕らはアニメ制作のプロなので、TVシリーズ化するうえで「最低限どこを拾っておけばいいか」というポイントはわかります。シリーズ構成の入江信吾さんは大変だったと思いますが、なんとかまとめることができました。
その後の演出では、そこを駆使しながら行間を読ませるような流れにしました。
とはいえ、綱渡り状態だったので僕も林さんも不安はものすごくありました。ずっと週刊連載をしているマンガ家さんのようなハラハラ感でしたね。
――そのほかアニメ化するうえで苦労された点はいかがですか?
宮
たくさんあるのですが、大きなところだと『消滅都市』の世界を紛れもない現実として扱わなければいけなかったことです。
本作独自の設定である「ロスト」ですが、僕らにとっても本当に起こった出来事であり、そんななかで生きているという気持ちでいられるように、常に考えていました。
――あの世界にいるんだと。
宮
ロストの規模感や人々のヒリヒリした感じがわかっていないと、ユキやタクヤたちに代わって表現できないと思いました。
そのうえで、もうひとつ生まれた苦労は、重苦しいだけのドラマにはしないことでした。
今言ったような世界観をそのままやろうとすると『はだしのゲン』のような非常にシリアスなものになってしまう。そうではなく僕らがつくるのは、今の時代を生きる若者の青春群像でなくてはならない。

――また違う見せ方が必要になりますね。
宮
シリアスに振り切るのではなく、多少のライトさをもってポップに描くところはポップに描く。そのバランスを保つのに苦労しました。
そして青春群像なので、この世界の天国と地獄を全て描き切るのではなく、そのなかで、もがきながらなんとかしようとする若者を描きたい。若い彼らだから「まだ希望はある」と突き抜ける突破力を持っているし、よくよく考えれば冗談を言えるような状況でもないところで、ふざけることもできる。
そういうところが物語の良い味付けになっていると思います。
――『消滅都市』の世界を守るために設けたバランスですね。長い制作期間中にブレないでいるのは確かに苦労を感じます。
下田
ほかに苦労というと……わかりやすいのは本読み中に“ケンカ”になることですね(笑)。
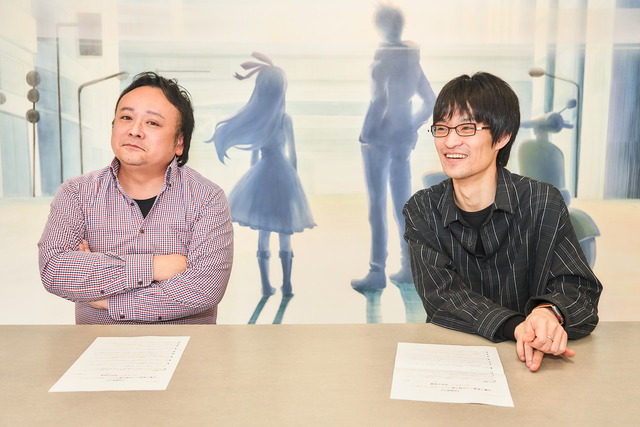
――それは、他のスタッフさんへのインタビューでも挙がっていました。ともあれ、それぞれ主張や考えがあるから起こる前向きな議論だったと聞きました。
下田
そうなんですよね。みんなが自分の役割と責任に対して真摯だったので。あれは作品を良いものにしなければという強い気持ちのあらわれだったと思います。
宮
そうですね。あと「ゲーム」と「アニメ」それぞれのジャンルで長くやっているプロなので、どうしても相反する部分もあるんです。
実際に絵にならないとわからない、動かないとわからない、声がつかないとわからないといったこともあるので、話し合いの段階で「大丈夫です!」と僕が説得しても「本当に?」となってしまう。なので僕がその場でホワイトボードに絵を描いて探り合うこともありました。
→次のページ:ユキとタクヤが近づいてきてくれた