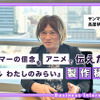ヤンマーホールディングスが製作・プロデュースを手掛けるオリジナルアニメ『未ル わたしのみらい』が4月2日から放送される。
本作のオープニング主題歌をバーチャルアーティストグループ「V.W.P」が担当することや、オムニバス形式のストーリーとして全5話で放送されることなどが話題となったが、特に2023年の製作発表時に異業種の同社がアニメ製作に参入することは、業界から驚きを持って迎えられた。
異業種のアニメ産業は難しいと言われ、しかも、一般的な商業アニメとは異なる目的、企業ブランディングのために作られるアニメであるために、余計に難しい面もあったかもしれない。この重責を担うことになった同作のプロデューサーは、『ガンダム』シリーズや『シティーハンター』のプロデュース、アニプレックスの統括など要職を経験してきた植田益朗氏だ。
アニメ業界の大ベテランが、このヤンマーのアニメプロジェクトにどんな可能性を感じたのか、話を聞いた。

オムニバスで「スタジオバトル」をやってみたかった
――ヤンマーから、アニメプロデュースの依頼を受けた時、率直にどう思われましたか。
植田ヤン坊マー坊のアニメを作るのかなと思ったんですが、どうも違うらしいと聞いて、なんだろうなと不思議でした。長屋さんからは、若い方のリクルートなどの観点で企業認知度を上げたいという話がありまして、それで最初に30秒のパイロットアニメを作りたいということから、この企画が始まっています。厳しいスケジュールだったのですが、たまたま自分の知っているCGスタジオが、予定していた仕事がなくなって空きが出たんです。そこに相談したらなんとか頑張ってみますと言っていただけて。
そこからいよいよ、アニメを本格的に作りましょうとなっていったんですね。それが2023年です。ご存じかと思いますが、日本ではとんでもない数のアニメが作られていて、スタジオのスケジュールはもう満杯なんですね。そういう中で、長屋さんのやりたいことと、現実的にできることを検討して、LAのアニメエキスポで発表することになりました。あの時はまだ本当に中身については何も決まってなかったんですよ。
――アニメエキスポで発表した時には、オムニバスになることも何も決まってなかったんですね。
植田はい。ぶっちゃけて言うと2023年の11月2日に緊急会議をしまして、スケジュールはもう絶対に後ろ倒しにできないという状況で、ある程度のクオリティを担保しながら作るには、1つのスタジオでは足りないと思ったので、5つのスタジオで1エピソードずつ作って、オムニバスでやることを思いつきました。
――1つのスタジオで全部作るスケジュールはとても抑えられないと。しかし、5つのスタジオを抑えるのも別の大変さがありますよね。
植田そうなんですよ。「手伝ってほしいのはこっちです」というスタジオばかりで。しかし、最終的にやってくれたスタジオは面白がってくれて、積極的に手を挙げてくれたので本当に助かりました。
――それぞれのスタジオが、個別にストーリーも考えているのですか。
植田全体のストーリーは僕がコントロールしています。それがヤンマーさんの希望であったし、伝えたいことを伝えるという目的を達成する必要もありますので。結構骨太な、観応えのある内容になっています。全体のストーリーは僕がライターさんを入れて相談しながら、各エピソードの脚本以降を各スタジオの監督たちにお任せするという形にしています。
――では、各スタジオがある程度裁量を持って、独自のカラーを出しているわけですね。
植田そうですね。ロボットは共通のCGモデリングを渡してそれぞれテクスチャーをアレンジしています。それ以外のキャラクターデザインや背景など全てスタジオが独自に作っています。ある意味ではバラバラですが、ヤンマーの事業は1つではなく多面的に色々なことを展開していますから、作品も1つの色に染まっていなくてもいいと思いましたし、見比べる楽しさもあると考えました。
実際、完成した作品はどれも面白くて、オムニバスにして良かったなと思いました。以前から、1つの企画で色々なスタジオが作る「スタジオバトル」みたいなことをやりたかったんです。ある共通のテーマでスタジオごとにプロジェクトをやると、競争意識も出て手を抜けないぞとなる。視聴者も今度のスタジオはどうやってくるかなと毎回新鮮に楽しめると思うんです。
――ロボットの共通の設定などはどうされたのですか。
植田私は『機動戦士ガンダム』という作品でアニメ業界に足を踏み入れてしまい、抜けられなくなりまして、いまだにここにいるわけです。『ガンダム』はそれ以前のロボットアニメとは違い、設定をすごく緻密に作り込んで、リアリティがあるものとして出したことで支持されました。
今回の作品にもロボットが出るんですが、色々考えて、今回は逆に設定を細かく作り込まずに、オムニバスという企画の特徴も活かして、各スタジオの裁量に任せてみようと思ったんです。そうすることで、逆にロボットものという企画の可能性を拡げられると面白いかなと。だから今回の作品にはアンチガンダム的なところがあるんです。
――では、それぞれのエピソードで登場するロボットは異なるものになっているんですね。
植田プロローグを読んでもらうとわかりますが、今、地球の人口は80億人に達するようですけど、それだけの人間の数だけ「未ル」のロボットがあると、そういう風に思っていただいて、それが未来を描くということにつながると思うんです。
――これまで植田さんが手掛けてこられたロボットアニメとは一線を画す内容になりそうですね。
植田そうなんです。だからこれは結構な挑戦なんです。ロボットアニメもやり尽くされていますからね。人に寄り添うロボットというコンセプトで新しいものに挑んでみました。
モノ売りのためじゃないアニメがあってもいい
――ヤンマーという異業種とのアニメ制作で、何が大変でしたか。
植田ほとんどの方がやる気がありすぎて、逆に大変でした。初めて本格的にアニメに取り組むということなので、色々な意見が出るんです。アニメ業界の常識ばかり押し付けても面白くないですし、かといって、ある程度はこちらの業界のやり方についても知っていただく必要があります。
今回のアニメ製作の動機は純粋なビジネスではないので、そこは僕も大事にしたかった。そのことをヤンマーの社内にもぜひ広めたいので、社員の中で声優オーディションをやったりしました。結構上手い人がいて、声優の専門学校に行っていた人もいたりして。そうやって社内を巻き込んで全員参加という気分を作っていきました。
長屋さんというユニークな方が主導している企画ですし、こちらも色々なわがままを言わせてもらいました。3月に開催されたAnimeJapan 2025では痛トラクターを展示したり。乗って写真も撮影できるんです。そこでヤンマーが本気でアニメファンに向き合って、アニメを作っているんだというのを知ってもらおうという狙いです。
――ヤンマーのような異業種がアニメ業界に参入することで、業界内に新たな良い刺激が生まれる可能性はあるでしょうか。
植田刺激が生まれてほしいと思っています。僕も色々なプロジェクトをやってきましたけど、同じことはやりたくないタイプなんですね。テレビアニメは視聴率やマーチャンダイジングのために作るところから始まって、2000年代からコンテンツビジネスという側面で、パッケージ販売や海外に売っていくようになりました。発展はしましたが、結局はモノ売りですよね。今、過剰にモノ売りに行っているような気がします。これは業界にとって良くないかもしれない。似たような企画がいっぱい並んでしまうのも、売れるモノをとにかく作らねばならないからですよね。やっぱり、みんなで同じものばかり作っているのは、ちょっと悲しいですよね。ここは少しでも変えていきたい。
ヤンマーさんは、会社の価値を向上させるブランディングのためにアニメを作るわけです。これは消費財としてアニメを作るというのとは、ちょっと違うんです。こういう形で新しい可能性を示してくれるのは有意義だし、なんとしてもこれを成功させたいと思っています。ヤンマーが単純にコンテンツビジネスに参入するということじゃなくて、ブランディングの結果、認知度が上がって会社に貢献するという最初の目的がぜひ達成されてほしい。そうすることで他の企業もブランディングとしてのアニメの可能性を考えてくれるようになるかもしれない。これは、新しいアニメとの向き合い方だと思うんです。
――ブランディングのために作るアニメというのが広まれば、アニメ業界に何かのブレイクスルーを起こすかもしれませんね。
植田はい。アニメ業界でも、このプロジェクトに期待をしている人たちもいるんです。ヤンマーという110年の歴史を超える企業が、アニメという選択をしたこと自体に意外性があるし、これは新興企業が金の匂いを嗅ぎ付けてやってきたというのとは違うと思うんですよ。このアニメがヤンマーにとっての収益源になるわけではないですから。これを植田の、アニメ業界に対する最後の置き土産としたいですね(笑)。